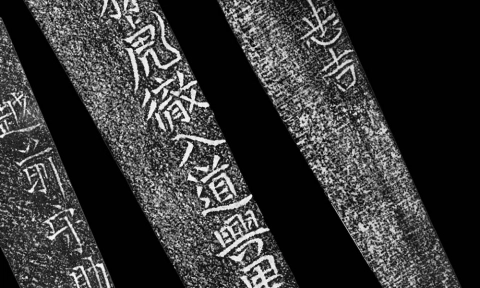日本刀と慣用表現その2
2021/11/19

1.土壇場
江戸時代には、罪人を処刑するため斬罪の刑場に、土を盛って壇を築きそこで刑の執行をしていました。刀の茎(なかご)に試銘で胴を何体斬ったかという試し切りもこう言った場所で行われていました。この土を盛った壇、つまり土壇場まで来てしまったらもう逃げられない最期の時を迎えることから、これが転じてどうにもならない時や最後の決断を迫られたときに使う表現になりました。

2.相槌を打つ
日本刀を鍛錬する時、刀鍛冶の師匠と弟子が向き合って交互に鉄槌を打ち合う様子を相槌を打つといいます。これが転じて現代では、会話の際に、相手の意見や意向にうなずいたり、同意することを言うようになりました。
3.単刀直入
文字通り、たった一人で刀を携えて真っすぐ敵陣に向かって斬り込むことを言います。つまりいろんな策を講じたり、遠回りをして背後を狙ったりせず、真っすぐに急所を狙って向かっていく様子から、今では回りくどい前置きや余談を抜きにして、直接いきなり本題に入ることを指すようになりました。
4.両刀使い
いわゆる剣術の二刀流のこと、または二刀流を使う武士や剣士のことを指す言葉でした。そこから相反する二つの趣味や嗜好を持つこと、または持つ者を意味する言葉だったのですが、現代ではその意味よりは、異性と同性を同時に性的興味の対象とする人(いわゆるバイセクシャル)を主に指すようになりました。それとは別に、本来の意味であった「相反する二つの趣味や嗜好を持つこと、または持つ者」の意味として、最近では「二刀流」と呼ぶようになりました。二天一流の開祖で五輪書の著者としても知られる宮本武蔵も、剣を持てば二刀流ですが、書画などでも才能を発揮し文武両道の二刀流だったというわけです。

5.抜き差しならない
日本刀に錆が付いて、鞘が堅く締まって抜けなくなってしまった様子を言います。このことから、身動きがとれなくなってしまった状態を抜き差しならないというようになりました。
6.焼きを入れる
日本刀は、熱して赤らめた刀身を一気に水に入れて冷却し、焼き刃を入れ硬くすることを焼き入れといいます。この工程を行うことで斬味の鋭い刃ができるため、現代では気持ちがたるんでいる人に気合いを入れて、根性を叩き直すことを焼きを入れるというようになりました。